公共工事をめぐる談合事件が世間を騒がすたびに、当の建設会社などから決まって声が上がる。「予定価格と入札価格がほぼ一致するのは当たり前だ。落札率が99%でも談合ではない」。
予定価格とは、工事を標準的な方法で施工する際に必要となる原価と利益について、実勢価格の調査などを基に積算したもの。発注者が入札に先立って定め、落札を認める上限価格となる。落札価格を予定価格で除したものが落札率だ。従って、どの会社が受注しても、必要な原価と利益を見込めば予定価格に近くなるというのが先の主張だ。
もし落札率が99%の工事が当たり前ならば、どの建設会社が施工しても同じ構造物を同じ費用でしか造れないことになる。だとすれば、多少のむなしさは残るが、入札を実施する意味はない。各社が予定価格と同額で契約して、持ち回りで工事をすればよい。
一方、いまや各地で“脱談合”による落札率の低下が相次ぎ、落札率が99%の工事はめっきり少なくなった。逆に増えたのが、落札率が70%や75%といったいわゆる低入札工事だ。低入札は納税者にとってうれしいことかもしれないが、過度の競争は地方の雇用や経済などを担う建設会社を疲弊させる。
入札せずに、地域の工事は地域の会社に任せる――。東京ガスは2003年4月、小規模で定型的な工事の発注方法を変更した。施工区間が50m以下の導管の敷設工事が対象だ。
同社は営業地域を11に分割。建設会社同士が恒常的なJV(共同企業体)をつくれば、一つの地域内の工事は一つのJVだけに発注するようにした。施工区間の長さなどに応じて、単価契約で発注する。
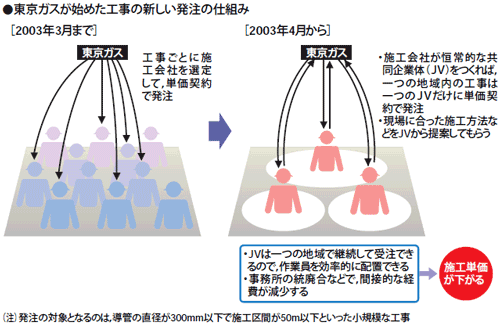
東京ガスのねらいは、入札の手間を省くことだった。さらに、施工単価を下げることにもつながった。理由は主に二つ。一つは、JVが一つの地域内で継続して受注できるので、作業員を効率良く配置できるようになったから。もう一つは、建設会社が各地域にそれぞれ設けていた事務所を統廃合して、間接的な経費を削ることができたからだ。
公共工事への投資が縮小するなか、建設会社同士がどこを競争して、どこを競争しないのか。入札や契約の制度をつくる発注者の責任は重い。

















































